朝起きて、真っ先に埼玉県北部地方の天気を確認した。
今日午後、行田市にある埼玉県立総合教育センターで研修会講師を務めることになっていた。
昨年の同じ時期にも行ったのだが、その時は今まで見たことがないドでかい「ひょう」が降ってきて、車がボコボコになるという大被害を受けたのだ。
その記憶があるので、今日は大丈夫かと天気を確認したのである。
結果、予報通り、やや曇りがちの天気で雨は一滴も降らなかった。もちろん「ひょう」もだ。
研修テーマは「SNSを利用した広報活動」である。
zoom形式の研修で、受講者は公立小中高及び特別支援学校の先生方である。
高校の先生方だけであれば、生徒募集のための広報活動に絞れるのだが、小中・特支の先生方には生徒募集はあまり関係ない。
まったく関係ないとは言えないが、高校に比べれば、重要性はそれほどでもない。
◆広報活動の対象
広報活動はステークホルダーとの良好なコミュニケーションを確立するための活動である。
ステークホルダーはさまざまな形で学校と関係を持っている人々で、生徒・保護者、卒業生をはじめ、地域住民、行政、企業、大学、マスコミ等々、非常に範囲が広い。
もちろん受験生・保護者、中学校・塾の先生などもステークホルダーに含まれる。
ステークホルダーごとに求める情報が異なるので、対象を意識した広報が必要である。
まずは主たる対象となるステークホルダーを定め。それに対する広報を中心に行う。
そして、手法に習熟し、ある程度結果が見えてきたら、徐々に対象を広げて行く。
以下、主な内容。
◆広報活動の目的
代表的なものを3つ挙げておく。
(1)ファンや理解者・協力者・支援者を増やす
(2)ブランドイメージの向上を図る
(3)リスクヘッジ
少子化が急激に進む中、各校は独自の資金調達ルートを確保しておく必要がある。
県・市町村の予算が縮小するのは間違いなく、施設設備等の更新や新設のための自主財源を用意したい。
その時、頼りになるのはファンや理解者・協力者・支援者である。
そのため、日頃から彼らに情報発信し、良い関係を築き、できれば資金面での支援者になってもらいたい。
東京大学などは、遺贈寄付の仕組みを作り、遺産まで寄付してもらおうとしている。国からもっとも資金を得ている東大でさえ、そこまで考えている。
ブランド=高級品ではない。
「安くて丈夫、高品質」もブランドである。
広報活動を通じ、「子供を伸ばしてくれる学校」、「保護者にも優しい学校」といった学校イメージを作って行く。
日頃から良い関係を築いておくと、いざという時(たとえば学校で不祥事が起きてしまった時など)に味方になってくれる。
広報活動にはリスクヘッジとしての機能もある。
◆SNSの活用
今までは紙媒体やホームページが主な広報媒体であったが、近年これにSNSが加わった。
さしあたり学校が利用しやすいのはInstagramである。
X(Twitter)はテキスト(文字)中心に発達してきた。
Instagramは拡散性に劣るが、その分炎上の危険性は低い。
TikTokはエンタメ性(娯楽性)が強すぎて広報には向かない。
◆ホームページとの棲み分け
速報性はSNSが勝っている。
ただしフローの情報として消費されて行く。
ホームページの強みはストックにある。
サーバー容量にも左右されるが、どこまでも詳しい情報をストックすることができる。
SNSできっかけを作り、情報の図書館とも言えるホームページに誘導する。
◆誰がやるか問題
組織で行うのが一つの理想だが、最初は個人から始めたほうがいい。
やってみたいと手を挙げた人にやってもらう(実験的)。
やってみればさまざまな問題点が明らかになる。
組織作りはそれからでも遅くはない。
◆中堅・ベテランが技術を習得する
若手教員のセンスは期待でき、技術的にも優れている。
が、彼らは総合的な判断力に欠ける。
若手が判断力を身に付けるまでの時間と、中堅・ベテランが技術を身に付けるまでの時間を比較すると、後者の方が圧倒的に短い。
スマホが使えれば誰でもできるのだから、まずは総合的判断力を持つ中堅・ベテランの力を活用しほうがいい。
ざっとまとめると以上の内容だ。
受講者の中には、日頃このブログをお読みになっている方もいたかもしれない。
このブログには、「学校ホームページ」「SNS」「生徒募集」というカテゴリーがあるが、今日話した内容はほとんどそこに書いてあることだ。
その日の思い付きで書いているので系統性がないのが欠点だが、少し時間がある時に過去記事を参考にしていただけると有難い。
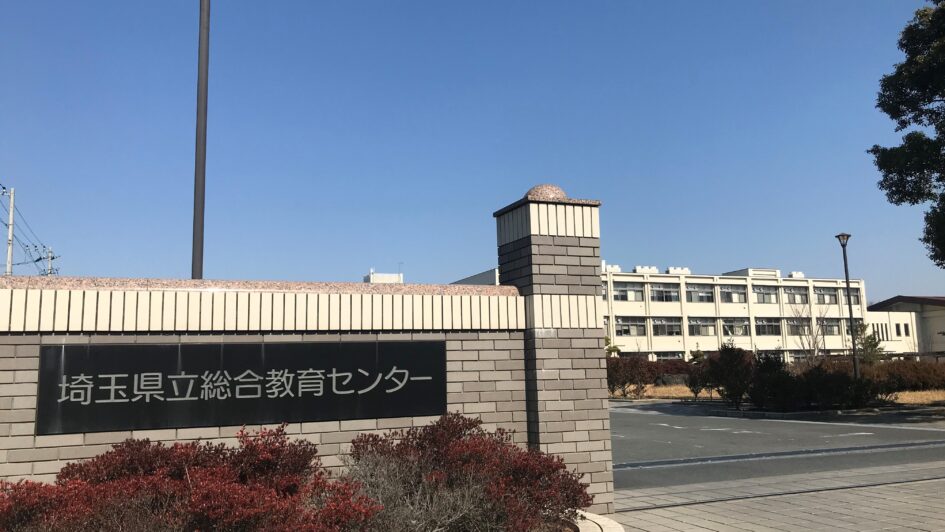

コメントを残す